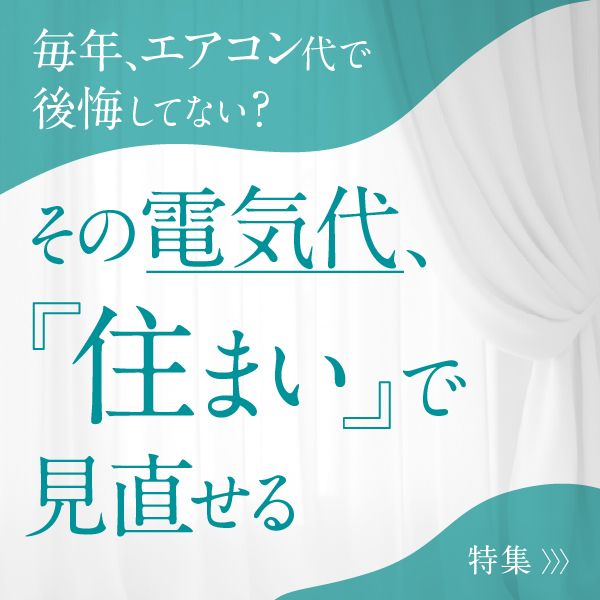不動産を検討する際によく使われる「坪」という単位ですが、一坪はどのくらいの大きさなのでしょうか。土地や建物の大きさを正しく理解することは、基礎知識として大切です。今回は、一坪を平米や畳数に換算したときの大きさや、住みやすい家の広さを考えるときの目安をご紹介します。ハウスメーカーの実例も参考に、理想の住まいを検討しましょう。
日本独自の単位「坪」とは
坪とは、日本独自の単位で面積を表す言葉です。「尺貫法」と呼ばれる日本古来の計算方法のなかで、面積を示す単位として「坪」が用いられてきました。測地用の慣用単位でもあり、旧土地台帳や旧家屋台帳でも見られます。
戦後に尺貫法は廃止となり、国際単位系に統一されたことで、現在は住宅建築や設計における正式な書面で「坪」は用いられなくなりました。しかし、現在でも「一坪〇〇万円」といったように使われるケースが多くあります。
ここからは、一坪の広さを正しく理解するために、平米(㎡)や畳に換算したときの大きさを解説します。
一坪は何平米(㎡)か?
一坪を平米にすると約3.31平米(㎡)です。具体的には、一坪は1辺が1.82mの正方形のため、平米に換算すると「一坪=1.82m × 1.82m = 3.3124㎡ ≒ 約3.31平米(㎡)」となります。
なお、坪数を平米数に換算する場合、坪数 × 3.31m = 平米数 で表せばよいと解釈しがちですが「一坪=3.31㎡」はあくまでおおよその数字であるため、注意が必要です。
3.31平米で坪数で計算をしてしまうと、坪数が大きくなるほど、平米数に誤差が生まれてしまうため、一般的には以下の計算式が用いられます。
<坪数を平米数に換算する場合>
例えば、30坪であれば、平米数は30坪 ÷ 0.3025 = 約99.17㎡となります。
一坪は何畳か?
一坪を畳数に換算すると約2.00畳になります。一般的に、畳数1畳=畳一枚分と考える方が多いですが、地域によって畳一枚の大きさが異なることを覚えておきましょう。地域などにおける畳の大きさの違いは以下の通りです。
<地域などにおける畳の大きさの違い>
名称
| 畳一枚の大きさ
|
|---|
江戸間(東日本エリア)
| 176.0cm × 横 87.8cm = 1.54㎡
|
中京間(東海エリア)
| 182.0cm × 横 91.0cm = 1.65㎡
|
京間(西日本エリア)
| 191.0cm × 横 95.5cm = 1.82㎡
|
団地間 (エリアに関係なく共営住宅・アパート・マンションなどで活用)
| 170.0cm × 横 85.0cm = 1.44㎡
|
上記のように畳の大きさは地域などによって違いがあります。しかし「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」においては、居室等の広さを畳数で表示する場合、畳一枚当たりの広さは、1.62㎡(各室の壁芯面積を畳数で割った数値)以上とされています。
この数値を踏まえると、一坪(3.31平米)は、約2畳と捉えてよいでしょう。
なお、坪数の換算表は以下の通りとなるため、参考にしてください。
坪数
| 平米数
| 畳数
|
|---|
1坪
| 約3.31㎡
| 2畳
|
2坪
| 約6.61㎡
| 4畳
|
4坪
| 約13.22㎡
| 8畳
|
6坪
| 約19.83㎡
| 12畳
|
8坪
| 約26.44㎡
| 16畳
|
10坪
| 約33.05㎡
| 20畳
|
15坪
| 約49.58㎡
| 30畳
|
20坪
| 約66.11㎡
| 40畳
|
25坪
| 約82.64㎡
| 50畳
|
30坪
| 約99.17㎡
| 60畳
|
坪単価とは?坪単価の計算方法
坪単価とは、土地や建物の床面積一坪当たりの価格や建築費のことです。土地であれば「一坪の価格」、建物であれば「建物一坪あたりの建築費」となります。特に建物における坪単価は、施工会社を比較する一つの目安となるため気になる方も多いでしょう。
建物の坪単価を算出するための計算式は以下の通りです。
床面積とは、全ての階の床面積を合計したものを指します。例えば、本体価格3,000万円で延床面積が30坪だった場合、計算式は3,000万円÷30坪となり、坪単価は100万円と分かります。
しかし、坪単価は施工会社によって基準が異なることを理解しておきましょう。例えば、「本体価格に含まれる内容が違う」「延床面積に含まれない工事部分を加えた施工面積で算出している」などさまざまなケースがあります。
また、同じ仕様や設備であっても、延床面積が小さくなるほど坪単価が高くなることも覚えておきましょう。これは、床材や壁材の費用が減っても、本体価格の3割程を占めるキッチンやお風呂といった設備機器の費用は減らないため、相対的に見て延床面積が小さくても坪単価が高くなるのです。
坪単価で施工会社を比較する場合、仕様や設備が同一かを確認するだけでなく、坪単価の算出方法を把握し、同じ条件で比較検討していくことが重要となるでしょう。
住みやすい家の広さを考えるときの目安
一坪の大きさが理解できても、どのくらいの大きさを基準に物件を検討すればよいのか気になる方もいるでしょう。
国土交通省では、住生活の安定や向上を促進するために「住生活基本計画」を発表しています。そこでは、居住人数に応じた最低限必要な面積なども提示されています。ここからは、国土交通省の資料を参考に、住宅の大きさの目安を見ていきましょう。
居住面積水準
国土交通省では、居住面積の目安を「最低居住面積水準」と「誘導居住面積水準」の2つの種類に分けています。
さらに「誘導居住面積水準」は、都市部を中心を想定した「都市居住型」と、郊外及び都市部以外の地域を想定した「一般型」の2種類に区分けされています。
<最低居住面積水準> 健康で文化的な住生活の基本とし、必要不可欠な住宅面積に関する水準 - 単身者は25㎡(約7坪・約14畳)
- 2人以上の世帯は、10㎡ × 世帯人数 + 10㎡
(例:大人2人の場合 10㎡ × 2人 + 10㎡ = 30㎡ )(約9坪・約18畳)
|
<誘導居住面積水準> 豊かな住生活の実現の前提として、多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる住宅面積に関する水準 └ 都市居住型(都心とその周辺の共同住宅居住(マンションなど)を想定) - 単身者は40 ㎡(約12坪・約24畳)
- 2人以上の世帯は、 20㎡ × 世帯人数 + 15㎡
(例:大人2人の場合 20㎡ × 2人 + 15㎡ = 55㎡)(約16坪・約32畳)
└ 一般型(郊外や都市部以外における戸建住宅居住を想定) - 単身者は55 ㎡(約16坪・約32畳)
- 2人以上の世帯は、 25㎡ × 世帯人数 + 25㎡
(例:大人2人の場合 25㎡ × 2人 + 25㎡ = 75㎡)(約22坪・約44畳) |
なお、世帯人数において子どもは、3歳未満は0.25人、3歳以上6歳未満は0.5人、6歳以上10 歳未満は0.75人として算定します。
夫婦2人世帯なら25坪程度・子育て家庭なら30坪程度
国土交通省の資料をもとに考えると、住みやすい居住面積は「夫婦2人世帯は25坪程度」「子育て世帯は30坪程度」(子ども1人から2人想定)が一つの目安となるでしょう。
特に戸建て住宅の場合は、居住空間の広さにこだわる方が多く、マンションに比べてゆとりのある空間を求める傾向にあるようです。子育て世代が戸建て住宅を検討する際は、30坪程度あると快適な空間を実現しやすいでしょう。
ハウスメーカーが手掛ける30坪の実例紹介
ハウスメーカーが手掛ける30坪程度の住宅では、どのような家づくりが可能なのか気になる方もいるのではないでしょうか。ここからは、ハウスメーカーが手掛けた30坪前後の住まいの実例をご紹介します。
土間と一体のLDKと屋上。30坪で多様な過ごし方を実現
延べ床面積31.2坪の実例では、土間と一体のLDKと屋上を確保し多様な過ごし方を可能にしたハウスメーカーがあります。設計の自由度や耐震性能の高さ、一年中快適に過ごせる高水準の断熱性能によって、オープンな空間での住み心地の良さを実現しています。
効率的なプランニングで30坪以下でも大空間LDKを形に
延べ床面積26.7坪の住宅であっても、3LDK+小屋裏部屋の住まいの実例もあります。スペースを無駄なく活用することで大空間なLDKを形にしました。また、収納の取り方を工夫することで、限られたスペースであっても、スッキリで広々暮らせる間取りとなっています。
ハウスメーカーでは、一人ひとりの条件や希望に応じて、家づくりのプロが多彩なアイデアを詰め込み、理想の暮らしを実現するお手伝いをしています。気になるハウスメーカーが見つかったら、カタログを取り寄せたりモデルハウスに足を運んでみたりしてはいかがでしょうか。
一坪の大きさを理解して理想の住まいを実現しよう
一坪は「平米数に換算すると3.31㎡」「畳数に換算すると2畳分」です。不動産情報を見るときは、坪数の大きさを理解して確認できると、物件の内容を把握しやすくなるでしょう。また、家づくりを進めていく上で、実際にモデルハウスなどを見学することもおすすめです。内見を通して坪数や畳数の広さを肌で感じることでイメージが付きやすくなります。住まいの大きさや暮らしやすい間取りに悩んだら、ハウスメーカーなどプロの力も借りながら、理想の暮らしを実現できるとよいですね。